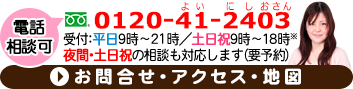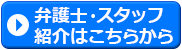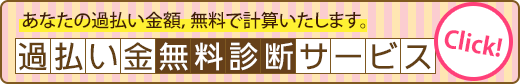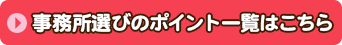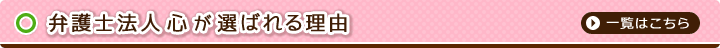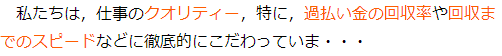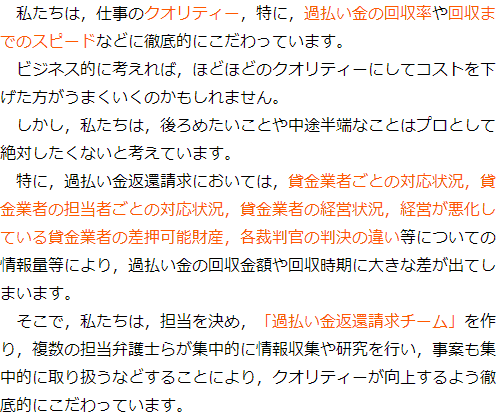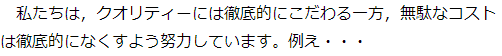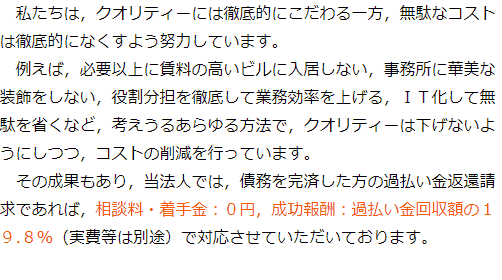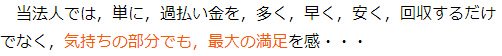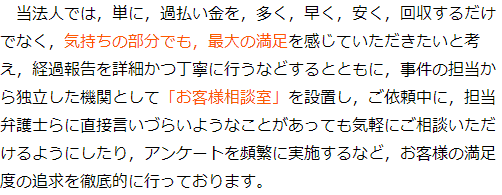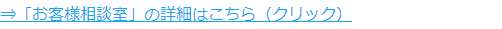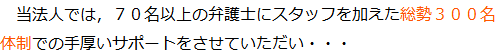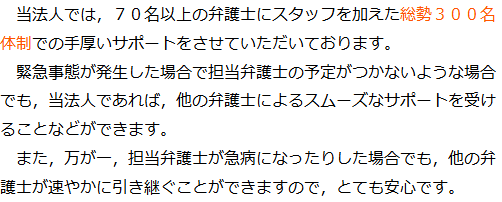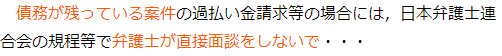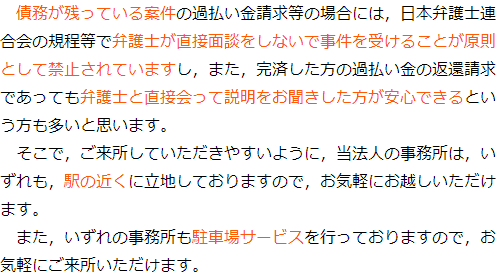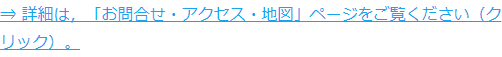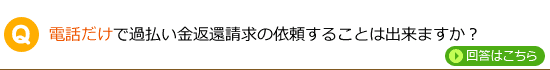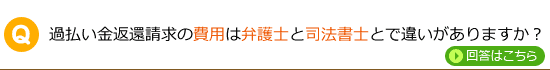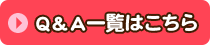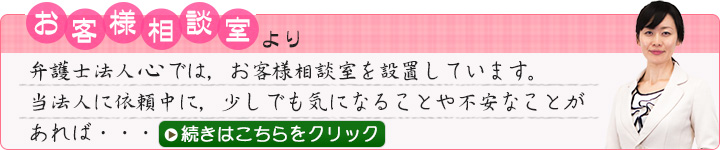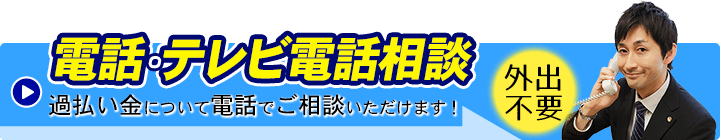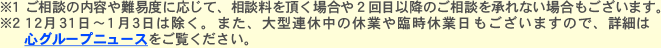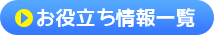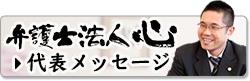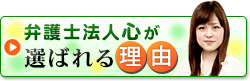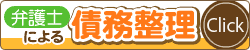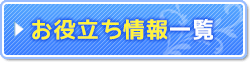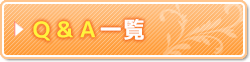完済した方の過払い金は電話相談可能です
事務所までご来所いただくことなく手続きを進めることができますので,お気軽にご利用いただけます。過払い金のご相談をお待ちしています。
過払い金が発生する可能性があるのはどんな人か
1 過払い金が発生する可能性がある人

貸金業者、クレジットカード会社から、制限利率を上回る利率での借り入れをし、利息を支払っていた場合に、過払い金は発生します。
一般的には、平成18年以前に、貸金業者やクレジットカード会社から借入と返済を行っていた人には、過払い金が発生している可能性があります。
以下、詳しく説明します。
2 過払い金発生の仕組み
貸金業者やクレジットカード会社が金銭を貸し付ける場合、法律によって利率の上限が定められています。
仮に法律で定められた利率を超えた利率で金銭消費貸借契約を締結したとしても、制限利率を超えた部分は無効とされます。
つまり、制限された利率による利息を超えた利息を支払った場合、超えた部分については無効な契約に基づくものとなり、貸金業者側としては法律上の原因なく受け取った金銭となります。
これを不当利得といい、不当利得については、支払った側が返還を求める権利を有します(法律上は、過払い金の返還を求めることは、不当利得返還請求となります)。
3 過払い金が発生していた時期
貸金業者、クレジットカード会社により多少異なりますが、概ね平成18年以前は、29%など、制限利率を超えた利率での貸し付けを行っていました(いわゆるグレーゾーン金利)。
制限利率を超えた利率でお金を借りていた場合、返済する際に利息を支払うことになりますが、支払った利息の一部が過払い金となります。
平成18年を境に、貸金業者、クレジットカード会社は、一斉に利率を法定された上限まで引き下げました。
そのため、法定の上限の利息での借入しかしていない場合、過払い金は発生しないことになります。
平成18年というと、すでにかなり昔のことになりますので、正確な借入開始時期を覚えていらっしゃらない方も多いです。
そのため、10年以上前から借入をしていた覚えがあるという場合には、とりあえず貸金業者、クレジットカード会社から取引履歴を取り寄せて、過払い金の有無を確かめておくのがよいです。
過払い金返還請求を行うメリット・デメリット
1 過払い金返還請求のメリット

過払い金返還請求をするメリットは、金銭を取得できる(可能性がある)ことに尽きます。
過払い金は、本来であれば貸金業者等に対して支払う必要のなかった金銭です。
別の観点から見ると、貸金業者等が本来は請求してはならない違法な利息部分に該当する金銭ですので、当然返してもらうよう要求することができます。
専門的な用語で表現すると、不当利得返還請求権という権利に基づいて、返金を要求できます。
また、不当利得返還請求権に基づく金銭の請求については、民法所定の利息も請求することができます。
つまり、理論上は、実際に払いすぎた金額以上の金額の支払いを請求することができます。
2 過払い金返還請求のデメリット
⑴ クレジットカード会社の場合、債務を完済している場合(いわゆる完済過払い)であっても、会社の運用によっては、当該クレジットカードの使用ができなくなることがあります。
普段の生活において、当該クレジットカードをメインのカードとして使用されている場合、不便になります。
⑵ 債務を完済していない場合(いわゆる残あり過払い)、過払い金と残債務とを相殺し、残債務を減らすという形になりますので、債務整理の一種となります。
そのため、信用情報センターに登録されることがあります。
⑶ また、過払い金返還請求をしたとしても、計算上の過払い金及び利息の満額をスムーズに支払ってくれる貸金業者等は非常に少ないです。
まずは、元金の〇割なら2か月以内に支払うというような提案をされることが多く、これだけでも不快な思いをされる方もいらっしゃいます。
満額を受け取るには、訴訟を提起しなければならないことも多く、心理的負担も生じます。
取引の分断や、貸付停止措置の存在等、過払い金返還請求を拒否する論点が存在する場合も、基本的には訴訟を提起して請求することになります。
この場合、貸金業者等の側も全面的に争うことがあり、訴訟が長期間にわたる場合もあります。
残債務がある方へ
1 残債務がある過払い金返還請求は、任意整理に近い性質がある

借入金債務が残っている場合や、クレジットカードの立替金(いわゆるショッピング債務)債務が残っている場合であっても、過払い金調査、返還請求をすることはできます。
もっとも、信用情報に事故情報が記載されることがあるので注意が必要です。
その理由は次のとおりです。
借入金債務や立替金が存在している場合は、過払い金が存在すると、相殺することになります。
借入金債務が存在している場合、過払い金の計算をすると、すでに残債はなく、過払い金のみが存在するということもあります。
いずれの場合も、現時点での借入金債務や立替金債務を減らすことになります。
そのため、残債務が存在する場合の過払い金返還請求は、任意整理と同様の性質を持ちます。
2 具体的な過払い金請求
⑴ 借入金債務のみ存在する場合
過払い金の計算をした結果、すでに残債務はなくなっており、過払い金のみが存在している場合、残債務がない場合の過払い金返還請求と同様に、過払い金の返還請求をします。
多くの場合、任意交渉を行い、支払額等に折り合いがつかない場合には訴訟を提起するという流れになります。
過払い金の計算をした結果、残債務は存在するものの、現在の残債務よりも債務額が減るという場合は、実質的には債務の減額交渉を行うことになります。
⑵ 借入金債務とは別に、立替金債務がある場合
一般的に、借入金債務の返済によって発生した過払い金は、立替金債務とは別個の法律関係に基づくものです。
そのため、過払い金返還請求権に基づく債権と、立替金債務は、両立する状態になります。
もっとも、実務上は、相殺をする形になります。
過払い金が100万円あり、立替金が40万円あるという場合は、立替金全額を過払い金で相殺したうえで、残りの60万円の支払いを受けるという形になります(実際には、交渉が発生するので、訴訟を提起しない限りは、満額の支払いを受けることは難しいです)。
逆に立替金が100万円あり、過払い金が40万円であるという場合は、過払い金分を減額した残りの立替金について、60分割等で支払うよう任意交渉を行うという形になります。
過払金返還請求が難航するケース
1 過払金は、必ずしもすぐに取り返せるのではない

過払金返還請求をする際は、まず貸金業者等に対して、取引履歴の請求をします。
この取引履歴をもとに、引き直し計算というものを行い、過払金の有無と、過払金が存在する場合にはその金額を割り出します。
その後、貸金業者等に対して過払金返還請求を行うという流れになります。
ところが、過払金返還請求をした段階になって、貸金業者側が、支払いに応じない、または一部しか返還しないと主張することがあります。
このような場合、訴訟を提起して争うことも多いです。
では、実際に、どのような要素があると、貸金業者側が争ってくるのか、代表的なものを説明します。
2 完済による取引の分断
最近は争われることは少なくなりましたが、一度完済してから、再度借入を開始した場合、一度完済した日が10年以上前であると、完済以前の過払金請求権が時効によって消滅すると主張されることがあります。
これに対しては、一度完済していても、一連一体の取引であるとして、完済前の部分についても消滅時効は完成しないという反論をします。
もっとも、理論上は分断期間がどれだけ長くても一連一体の取引であると考えることができますが、実際には、分断期間が長い場合、一連一体と判断されない場合もあるので注意が必要です。
3 貸付停止措置
貸金業者は、借主の信用情報等に応じて、貸付を停止することがあります。
そして、貸付停止の日から、過払金返還請求権の消滅時効が進行すると主張してくることがあります。
この点については、長い間借主と貸金業者の間で争われてきました。
一時期は、貸付停止の日ではなく、最後の取引の日から消滅時効が進行するという裁判例が多く、争われることも減っていました。
もっとも、最近は、貸付停止の日から過払金返還請求権の消滅時効が進行すると判断する裁判例も出てきています。
そのため、訴訟等で激しく争われることも想定されます。
4 キャッシング回数指定払いとリボ払い
クレジットカード会社から取引履歴を取得すると、キャッシングの返済方式ごとに履歴が分かれていることなどがあります。
大きく分けて、借り入れた金銭を、回数を指定して(1回払い含む)返済する方式と、1回あたりの返済額を指定して返済する方式(リボ払い)があります。
そして、クレジットカード会社は、一つの契約、一つのカードでの取引であるにもかかわらず、回数指定払いとリボ払いは別個の取引であることを主張することがあります。
これにより、借主側が主張する過払金の金額よりも、大幅に低い金額になることがあります。
これも非常に大きな争点であるため、訴訟で真正面から争われることがあります。
お金の借り入れができなくなったことがある方へ
1 貸金業者等による貸し付けの停止

貸金業者やクレジットカード会社は、契約があっても、突然貸し付けを停止することがあります。
このことは、契約書に記載されていることも多いです。
借主の勤務先、収入、借入額などの属性情報や、貸金業者やクレジットカード会社の経営状況などを勘案し、借入可能額を引き下げたり、貸し付けを停止したりします。
これは、回収不能リスクのある借主に対して、一定額以上の貸し付けを停止することで、自社のダメージを回避するという考えに基づくものです。
2 貸金業者等の主張
貸金業者等による貸し付けの停止は、過払い金返還請求権の消滅時効との関係で問題となります。
過払い金返還請求権の消滅時効は、通常は最後の取引の日から進行します。
ところが、貸金業者等が貸し付けの停止をした日が10年以上前であった場合、最後の取引(返済)の日が10年以内であったとしても、貸金業者等は消滅時効の主張をすることがあります。
具体的には、過払い金に関する重要な判例(最一小判平成21年1月22日)が、「借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」から消滅時効が進行するという趣旨の判断をしたことを捉え、取引停止措置によって新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったという理屈で、消滅時効が進行するという主張をします。
3 ここ数年、争いが再燃している
取引停止措置による消滅時効は、昔から大きな争点であったものの、近年では借主側が勝訴することが多く、取引停止措置が消滅時効の起算点にはならないという方向で固まってきたかのように見えました。
しかし最近、取引停止措置による消滅時効の進行を認める裁判例が散見されるようになりました。
貸金業者等は、これらの裁判例を前面に押し出し、訴訟の場で証拠として大量に裁判官に見せつけることで、印象操作を図る場合もあります。
具体的に争われるポイントは、①取引停止措置によって新たな借入金の発生が見込まれなくなったといえるか否か(再度借入が復活する可能性との関係)、②取引停止措置がなされたことを借主が認識する必要があるか否か、です。
立替金債務がある場合
1 貸付金と立替金

クレジットカード会社等に対する債務は、大きく2つに分けられます。
一つは、クレジットカードでお買い物などをされた際に、後日請求されるタイプのものです。
これは、いったんクレジットカード会社が買い物等の費用を立替えているので、立替金という性質があります(ショッピング債務と呼ばれることもあります)。
もう一つは、カードを使って、ATMや店頭などでお金を借り、後日返済するタイプのものです。
これは、文字とおり貸付金という性質があります(キャッシング債務と呼ばれることもあります)。
このうち、過払金が発生するのは、通常貸付金の方となります。
グレーゾーン金利でクレジットカード会社等からお金を借り、返済する際に法定利率以上の利息を支払った場合に過払金が発生します。
2 過払金と立替金との併存
あるクレジットカード会社から取引履歴を取得し、引き直し計算をした結果、過払金が発生していたとします。
そして、同時に立替金債務も存在していたとします。
これらは、法的な性質は別々ですので、併存しうる存在です。
つまり、クレジットカード会社に支払わなければならないお金がある一方で、逆に支払いを求めることができるお金があるという状態です。
3 実際に過払金を請求する際の扱い
立替金と過払金は、法的には別個の存在です。
そのため、理論上は、過払金の返還だけを請求することはできます。
しかし、多くの場合、クレジットカード会社は、立替金との相殺を主張します。
立替金よりも過払金の方多い場合、過払金から立替金を差し引いた残額について、返還を受けることになります。
逆に、過払金よりも立替金の方が多い場合、立替金から過払金を差し引いた残額を返済していくという形になります。
相殺は、借主側からも行うことができます。
クレジットカード会社が提案した過払金返還額に納得がいかない場合、訴訟を提起して請求することがあります。
その際、立替金債務もあることを主張したうえで、これと過払金の相殺の主張をします。
過去のできごとによっては過払金返還が難しくなる
1 過払金返還請求の基本

過払金は、おおむね平成18年以前から、貸金業者等との間で、グレーゾーン金利での借入れと返済を繰り返していた場合に発生します。
グレーゾーン金利と法定金利との差額が、過払金の発生の元となります。
貸金業者等から取り寄せた取引履歴をもとに、引き直し計算というものを行って、過払金の発生の有無を調べます。
引き直し計算の結果、過払金が発生していれば、貸金業者等に対して返還を求めていくという流れになります。
ところが、過払金が発生していたとしても、一定の出来事があった場合には、貸金業者等が返還に応じないことがあります。
どのような出来事があると、過払金返還請求に応じないのか、代表的なものについて説明します。
2 取引停止措置
貸金業者等は、借主の債務額や、収入の状況等を考慮し、貸付を停止することがあります。
そして、貸付を停止した日をもって、新たな貸付が見込まれなくなったとして、過払金の消滅時効が進行すると主張することがあります。
貸付停止は、借主が明確に認識していることは少ないです。
ATMなどで発行される取引明細書の融資可能額の文字が消えているのみであったり、貸金業者等内部の処理であったりするため、借主は貸付停止措置がとられたという記憶がなかったりします。
それにもかかわらず、突然消滅時効の主張がなされるため、とても面食らうことがあります。
この争点については、昔から借主と貸金業者等との間で強く争われており、裁判例も割れています。
そのため、貸付停止がなされた可能性がある場合、過払金を取り戻すには大きな労力を要する可能性があります。
3 キャッシングの回数指定払いとリボ払い
クレジットカード会社からお金を借りると、返済の方法を借主が選択できる方式になっていることがあります。
借入れた金銭を、一定の回数(一回払い含む)に分けて支払う回数指定払いと、一定の金額を毎月支払って返済するリボ払いが選択できるということがあります。
多くの場合、同じ契約のもと、同じカードで借り入れた際に返済方式を選択できるようになっています。
借主から見たら一つの借入に対して、返済方法を変えているだけに過ぎないのですが、クレジットカード会社に対して過払金返還請求をすると、回数指定払いとリボ払いは別々の取引であることを主張し、過払金の返還を拒否することがあります。
この争点も、借主とクレジットカード会社との間で強く争われる傾向にあり、場合によっては長期間の訴訟を行う必要があります。
過払金返還請求の際の留意点
1 借入開始時期によって過払金の有無は異なる

過払金は、貸金業者が違法な利息を取っていた場合に発生します。
違法利率のもとで支払った利息と、法定制限利率で支払った場合との差額が過払金になるためです。
そして、違法な金利で貸し付けを行っていた貸金業者も、おおむね平成18年を境に、法定制限利率での貸し付けに変更しています。
そのため、平成18年以降に借り入れを開始した方は、過払金が発生している可能性は高くないといえます(貸金業者によっては、平成20年くらいまで違法金利で貸し付けていることもあります)。
そのため、平成25年に借り入れを開始したなど、明らかに平成18年よりもだいぶ後になってから借入を開始した場合は、過払金の調査をしても望ましい結果は出ないかもしれません。
2 和解するか、判決にするか
過払金調査の結果、過払金が発生していることが分かった場合、貸金業者に対して返還請求をします。
後述する争点がない場合でも、基本的に貸金業者は、任意の支払いにおいては満額を支払うことはありません。
おおむね、元金の6~8割程度の支払い(そのかわり、1~3か月以内程度で支払う)を提案してきます。
この内容で問題なければ、和解契約を締結し、支払いを受けて終了となります。
提示金額では納得がいかない場合、訴訟を提起して、民法所定の利息含めて満額の支払いを請求します。
実際には、訴訟の話をすると提示金額が上がり、それで和解するということもあります。
また、訴訟提起後に、より良い条件が提示され、訴外和解を成立させて訴訟を取り下げるということもよくあります。
3 争点が存在する場合
過払金請求の際、貸金業者側が、過払金を支払わない理由(争点)を主張してくることがあります。
具体的には、取引の分断、取引停止措置、和解契約の存在、キャッシング一括払いとリボ払いの個別計算などが挙げられます。
このような主張がなされた場合、任意での支払いは望めないため、即座に訴訟を提起するということを行います。
過払い金返還請求を思い立ったら
1 過払い金返還請求のきっかけ

もしかしたら自分にも過払い金があるかもしれない、と思い立つことがあると思います。
そう思われるきっかけは人それぞれです。
以前から、過払い金があるのは知っていたけれども、行動までは起こせていなかったというケース。
テレビCMや、Web広告を見て、とりあえず過払い金があるか否か調べてみようと思ったケース。
過払い金の調査と、その結果もし過払い金があったら返還請求をしたいと思った場合、次に必要な情報を整理します。
整理すべき主な情報は次のとおりです。
2 過払い金がある可能性のある貸金業者がどこか
まず、そもそもどの貸金業者に対して借入と返済を繰り返していたかという情報が必要です。
以前から借入をしていた貸金業者のカードや利用明細などを探して、ピックアップするとよいです。
3 借入開始時期
過払い金が発生するのは、おおむね平成18年以前から借入と返済を行っていた場合です。
そのため、平成25年くらいから借入をしていて、利息も制限利率内など、明らかに過払い金がないと思われる貸金業者は候補から外れます。
借入開始時期を正確に思い出せないが、だいぶ前だった覚えがあるという場合には、とりあえず調査を行うことをおすすめします。
4 途中完済の有無
途中で完済した可能性がある場合、仮に過払い金があっても、貸金業者が消滅時効などを主張してくることがあります。
途中完済の情報があれば、そういった主張が予想できるため、事前に貸金業者と争う準備をしておくことができます。
5 取引停止の有無
最終取引以前に取引停止(借り入れができず、返済しかできない措置)になっている場合、貸金業者は取引停止があった時から消滅時効が進行すると主張することがあります。
6 和解の有無
返済の途中で、過去に任意整理(和解)をしている場合、貸金業者は過払い金が消滅していることを主張してくることがあります。
そのような場合、本当は和解の時点で債務は存在せず、むしろ過払い金が存在していたことから、和解が錯誤によって無効であることを主張するなどの準備が必要となります。
過払い金請求のための履歴開示
1 取引履歴の開示

過払い金請求を行う第一歩として、過払い金の有無と、ある場合にはその金額を計算する必要があります。
そこで、まずは貸金業者から取引履歴というものを取得するところから始めます。
取引履歴は、貸金業者との取引の履歴を示したもので、いついくら借りたのか、そしていくら返済したのか、返済した金銭のうち元金部分と利息部分はいくらであったのかが示されていることが多いです。
取引履歴から支払った利息が分かりますので、引直計算を行い、過払い金がいくらあるかを計算します。
貸金業者は、貸金業法という法律により、取引履歴の開示を求められた場合には、応じる義務があるとされています。
2 ご自身で取引履歴の開示をする際の注意点
取引履歴の開示は、弁護士や司法書士に依頼して請求するほか、ご自身で請求することも可能です。
ご自身で取引履歴の請求をした場合、貸金業者から、和解を提案されるケースもあります。
和解がご自身にとって有利なものなのか否かが判断できない以上は、和解に応じるべきではありません。
一度和解をしてしまうと、本来返還を求めることができるはずであった過払い金を後から請求することは、非常に困難になります。
そのため、無理にご自身で取引履歴を請求するよりは、一度法律の専門家に相談した方が得策です。
3 取引履歴が開示されない場合の対応
最近はかなり減りましたが、一部の貸金業者においては、請求をしても全く取引履歴が開示されないことや、一部だけしか開示されないという場合があります。
貸金業者は、古い部分の取引履歴は残っていないので開示できないという主張をして、一部しか開示しないということがあるのです。
この場合は、開示されている部分から、残っている利用明細等を用いて、どのような取引がなされていたか推定して計算する方法があります。
または、開示されていない古い部分の取引については、引直計算をすれば残高が0円になっているものとみなし、開示されている最初の部分の残高を0円として引直計算を行う方法もあります。
ただし、過払い金が何円発生しているかを立証する責任は、過払い金の返還を求める側にあるとされています。
そのため、取引履歴が開示されない場合には、結果的に、本来ある過払い金の一部又は全部が認められない場合もあります。
過払い金の調査から取り戻すまでの流れ
1 まずはヒアリングによる大まかな調査を行う

過払い金は、多くの場合、平成18年頃までの間に借り入れを行い、グレーゾーン金利で借入と返済を繰り返していた方において発生するものです。
また、貸金業者や金融機関によっては発生しないこともありますし、借入なのか立替なのかによって、発生するか否かが変わります。
そのため、まずはお借入を開始された時期や貸金業者について、詳しく伺わせていただきます。
その結果、明らかに過払い金が発生しないケースであることもありますが、平成18年前後以前に借入を始めたというケースであれば、履歴を取り寄せて過払い金の有無の調査を開始します。
2 取引履歴の取得
過払い金の調査を弁護士にご依頼いただくと、さっそく弁護士から貸金業者等に対して、受任通知を送ります。
これにより、貸金業者等は取引履歴を開示します。
また、最後の取引が10年程度前であるという場合など、消滅時効が完成するおそれがある場合には、完成を防ぐため、内容証明郵便等を用いて催告もします。
取引履歴が取得できたら、引き直し計算と呼ばれる、利息制限法上の上限利息で返済した場合の計算を行います。
引き直し計算により、過払い金が存在する場合には、過払い金の金額が明らかになります。
3 貸金業者等への請求
過払い金の金額が明らかになりましたら、民法所定の利息とともに、貸金業者等へ返還請求を行います。
そうすると、貸金業者側は、支払金額を提示してくることがほとんどです。
任意の交渉において、満額が支払われるケースは、多くはありません。
元金の数十パーセント程度の金額が提示されることがほとんどです。
法的な争点がある場合には、かなり低い金額が提示されることもあります。
この提示の時点で納得できれば、和解を成立させて、返金を受けて終了となります。
納得ができない場合、再度交渉をするか、訴訟を提起します。
訴訟提起後、より有利な条件が提示されることもありますので、その条件で和解を成立させて、訴訟を取り下げる(正確には入金がなされたら取り下げる)こともあります。
判決まで進んだ場合、特に争点がなければ、元金及び民法所定の利息すべての支払いを受けることができます。
過払い金返還請求の際に貸金業者と争うことがある
1 過払い金返還請求で貸金業者側から反論されることがある

取引履歴を取得し、引き直し計算をした結果、過払い金が存在していることが判明した場合には、貸金業者に対して過払い金の返還を求めることができます。
もっとも取引履歴上法律的な反論が可能な事実が含まれていることがあり、このような場合には貸金業者側は反論したうえで支払いに応じないか、または低い金額での支払いを提案してくることがあります。
貸金業者によっては必ず決まった反論をすると決めていることもあるので、そのような貸金業者の場合は任意交渉を経ずに訴訟を提起することもあります。
典型的な反論としては次の2つがあります。
2 取引の分断
取引履歴を取り寄せると、借入と返済を繰り返す過程の中で、完済すなわち残元金が0になり、その後また借入をしている履歴が存在することがあります。
このような場合、貸金業者としては完済前の取引と再度借入をした後の取引は法律上別の取引であると主張することがあります。
つまり完済によって完済前の取引とその後の取引が分断されるという主張です。
そして完済した日が10年以上前である場合、完済前に発生していた過払い金は時効によって消滅するという主張をします。
このような場合、訴訟によって請求を行い訴訟において取引が分断されたといえるか否かは、完済後次の借入までの期間利率等の契約内容の変更や契約書の返還の有無などを総合考慮して判断されることになります。
3 悪意の受益者性
過払い金返還請求は、法律的には不当利得返還請求権という権利に基づいて行います。
そして訴訟の場合、過払い金の元金に完済の日の翌日から支払済みまで年5%の利息を付けて支払うよう請求します。
この5%の利息の請求は、貸金業者において法律上受け取ってはいけない金銭であると知っていた場合(これを「悪意の受益者」といいます。)に請求できます。
制限利息以上の利息を受け取っていた貸金業者は、通常利息制限法の制限を超えていることを知っているのですからほとんどの場合これに当てはまります。
しかしこれに対しては、多くの貸金業者が争います。
具体的には貸金業法と関係法令で認められている通りにしていたことや貸金業法の要件を満たしていないことについてやむを得ない事情があったことなどを主張することがあります。
仮に9年前に完済していたとした場合、年5%の利息が加わると貸金業者として支払う金額は大幅に増えることがあります。
そのため貸金業者としても強く争いたい論点となります。
貸金業者の主張が認められることは多くはありませんが、貸金業者側もビジネスである以上新しい理論を産み出しては主張します。
当法人の弁護士は最新の動向を研究し再反論によって過払い金の支払いを認めてもらうよう日々研究しています。
貸金業者が倒産すると過払い金が回収できなくなるため早めに相談を
1 ないお金の支払いを求めるのは困難

過払い金返還請求は、不当利得返還請求といい、請求される貸金業者側から見ると債務(支払わなければいけない金銭)です。
会社は、債務が支払い不能になると(債務超過)、倒産します。
過払い金返還請求の対象となる貸金業者が倒産すると、過払い金の支払いを受けることが困難になります。
正確には、倒産といっても、破産、特別清算、会社更生、民事再生など様々な法的手続きがありますが、いずれにせよ支払いを受けられる過払い金は大きく減ってしまいます。
有名な事件の一つとして、消費者金融の大手であった武富士の倒産があります。
この時は、過払い金の弁済率は3.3%となりました。
100万円の過払い金を有していた方であれば3万3000円、仮に1000万円の過払い金を有していた方であっても33万円しか返還を受けることができないことになります。
過払い金がある貸金業者が倒産すると、非常に大きな不利益が発生してしまいます。
2 倒産により過払い金が回収できなくなるリスクの回避
上記のように、貸金業者の倒産によって過払い金が回収できなくなるリスクをゼロにする方法はなく、リスクを回避できる確率を少しでも上げるためには、1日でも早く過払い金返還請求に着手するしかありません。
アコムやSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など大手消費者金融については、現在のところ過払い金返還請求には応じています。
また、大手のクレジットカード会社についても、現時点では過払い金返還請求について特に大きな問題が起きることは少ないです。
一方、中小規模の貸金業者においては、過払い金返還請求の過程において大幅な減額を求めてくることがあります。
これは、貸金業者の業界は、以前のように大きな金利をとることができなくなったことや、過払い金返還請求による出費がかさんだことなどにより、経営環境が厳しくなっているからであると考えられます。
大手企業であっても、この先ずっと現在の状態が保てるとは限りません。
過払い金があるかもしれないと思ったら、すぐに弁護士へ相談し、請求に着手するのが得策です。
過払い金返還請求には時効があるので注意
1 過払い金の時効

過払い金の返還を請求する権利は、正確には不当利得返還請求権といい、起算点から10年間が経過すると消滅時効が完成します。
そして、消滅時効の起算点は、最終取引日(債務を返済し終えた日=完済した日であることが多い)とされています。
言い換えますと、完済してしまってから10年を経過してしまった場合、過払い金の返還を求めることができなくなる可能性があります。
より正確には、最終取引日から10年以上経過していても、請求すること自体は可能ですが、貸金業者側において消滅時効が完成している旨を主張(時効の援用)するので、結果として返還を受けられないということになります。
2 完済日は正確な調査をしないと分からないことが多い
最近完済された方は問題ありませんが、数年前などに完済された方の場合、完済日がいつであるかを正確に把握されていることは少ないです。
記憶と実際の完済日が異なることもよくあります。
過払い金返還請求を行う場合、まずは貸金業者から取引履歴というものを取得します。
取引履歴には、取引開始日から完済までの間の金銭のやり取りがすべて記載されていますので、正確な完済日を知ることができます。
この取引履歴を見てはじめて、すでに消滅時効になってしまっていたり、または消滅時効が間近に迫っていることを知ったりすることもあります。
そのため、過払い金の返還請求をしたいと思ったら、すぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。
3 消滅時効が迫っている場合
取引履歴を取り寄せた結果、消滅時効が迫っている場合には、すぐに引き直し計算をして訴訟を提起します。
訴訟提起により、時効を中断することができるためです。
もっとも、取引履歴の取寄せや引き直し計算には2週間~2か月程度の時間を要することがあります。
消滅時効が迫っている可能性があるケースにおいては、取引履歴を取り寄せている時間的余裕はありません。
そのような場合、弁護士が受任したらすぐに貸金業者に対して、過払い金の返還請求する旨の内容証明郵便を送付し、一時的に時効が完成することを防ぎます。
この行為の効果は半年間となりますので、その間に取引履歴を取り寄せて訴訟の準備を行います。
過払い金について弁護士に相談した方がよい理由
1 過払い金の調査(取引履歴の取得及び検討)

過払い金の返還請求をする前提として、まず過払い金が存在しているか否かを調べなければなりません。
具体的には、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、その内容を元に計算をしなければ、過払い金が発生しているかを正確に把握することはできません。
取引履歴の取り寄せ自体は、借入れを行ったご本人様でも行うことができます。
しかし、取引履歴は貸金業者によってフォーマットが様々であるため、過払い金の有無や金額が書いてあるとは限りません。
取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算という作業を行って、初めて過払い金の有無と発生額が分かります。
この引き直し計算は煩雑な作業であり、専門家でない方が行うことは簡単ではありません。
早く正確に過払い金の発生の有無を調べるためには、まずは弁護士に相談することが大切です。
2 過払い金請求の手段(和解または訴訟)
⑴ 和解について
実際に過払い金が発生していた場合でも、貸金業者が全額をすぐに返してくれるとは限りません。
むしろ、利息込みで全額を支払ってもらえることは稀です。
貸金業者側もビジネスとして交渉をしますので、過払い金が発生していることが判明し、請求を行った場合、様々な対応をとります。
例えば、交渉述の一つとして、問題の早期解決のため、発生している過払い金7~8割の金額であればすぐに支払う代わりに、残りの部分は請求しない契約の締結を提案するというものがあります。
このような場合、応じてしまうと、当然ですが後日全額を返してほしいと再交渉することは不可能になります。
もちろん、和解にメリットがないわけではありません。
後述する訴訟による請求は、返還を受けられる金額は高くなるものの、解決まで数か月~1年程度と、非常に時間を要しますので、早急に金銭が必要な場合には和解をするというのも手です。
貸金業者からこのような和解を提案された場合、その場で決断するのではなく、まずは弁護士に相談してみましょう。
和解に応じることが得策であるのか、それとも後述のように裁判で争う価値がある事案といえるのかについて適切なアドバイスを得られるはずです。
⑵ 訴訟による請求
貸金業者が提示している和解案が、発生している過払い金の金額よりも大幅に少なく納得がいかない場合は、訴訟により過払い金の回収を行うという選択肢があります。
訴訟も、借入れを行った本人で行うことはできます。
もっとも、訴状を自身で作成し、決められたルールに則って証拠等を添付して訴訟を提起しなければならず、さらに期日には平日の日中に裁判所へ行く必要があります。
事前に調査しなければならないことが多いだけでなく、お仕事を休む必要があることもあります。
他方、過払い金の返還の訴訟を弁護士に依頼することで、このような負担のほとんどは解消されます。
また、訴訟になってからも途中で和解するという方法もあります。
この場合にも、弁護士をつけていれば和解に応じることのメリットやデメリットを把握することができます。
3 過払い金返還請求を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント
過払い金返還請求を行っている法律事務所は多数あります。
しかし、過払い金返還請求を含む債務整理を中心的に扱う弁護士が在籍し、債務整理のノウハウ、実績も十分であるといえる法律事務所は多くはありません。
過払い金返還請求を行うためには、時効に関する理論や交渉戦略など、様々なノウハウが必要になります。
当法人では、弁護士がそれぞれ得意分野を担当しており、当該分野を中心的に数多く扱う弁護士が在籍しています。
過払い金返還請求事件についても同様です。
柏近郊にお住まいの方で、過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合には、当法人にご相談ください。
過払い金返還請求と引き直し計算
1 初めに行うことは取引履歴の開示

過払い金がいくら発生しているのかを正確に把握するため、まずは取引履歴の取り寄せを行います。
これにより、いつから、どのくらいの利率で、何回返済したのか、返済した金額の合計はいくらであったのかが分かり、払い過ぎたお金の有無と金額を計算する手掛かりになります。
2 取引履歴を材料として過払い金を計算する
⑴ 取引履歴には過払い金の有無が書いてあるとは限らない
取引履歴は、貸金業者によって表示の仕方が違います。
基本的には社内で使われているデータか、それに一部加工を加えたものであることが多いので、貸金業者側のルールによります。
基本的には、いつ、いくらの利率で、何回返済したのかという取引の事実についての記録が記載されているのみです。
貸金業者の方から「あなたには過払い金がいくらあります」というように親切に教えてくれるわけではありません。
貸金業者によっては引き直し計算を行ったうえで履歴を開示してくれるところもありますが、必ずしもその金額が正確とは限らず、貸金業者側が主張する法的理論に則って計算されている可能性もあります。
そのため、いずれにしても、取引履歴取得後、これをもとに過払い金がいくら発生しているのかを計算する必要があるのです。
⑵ 引き直し計算
取り寄せた取引履歴から過払い金がいくら発生しているのかを計算する作業を、一般に引き直し計算といいます。
具体的には、実際に支払った利息とされる金銭のうち、本来利息として請求してはいけなかった金額部分を計算します。
⑶ 引き直し計算の手間について
引き直し計算の作業はかなり煩雑です。
引き直し計算のソフト自体はインターネット上にも存在してはいます。
もっとも、取り寄せた取引履歴をもとに、数年に渡る取引を一つ一つ打ちこんでいくのは膨大な作業となり、非常に時間も手間もかかります。
お仕事をされているなど、なかなか時間の作れない方の場合、なおさら辛い作業になりえます。
⑷ 引き直し計算の手間を省略するには
最も確実な方法は、過払い金の計算を含めて弁護士に相談することです。
弁護士に依頼した場合、取引履歴の取り寄せと引き直し計算の作業を弁護士側で行うこともできます。
さらに、過払い金が存在していた場合の貸金業者との交渉、訴訟による請求といった作業も、すべて弁護士が一貫して行うことができます。
過払い金の返還請求が可能な期間は、消滅時効の関係により、最終の取引から10年間となります。
実際に、時効直前となっていた過払い金も数多くあります。
過払い金が存在する可能性があるとお考えでしたら、まずは弁護士にご相談ください。
取引履歴の取り寄せについて
1 過払い金に関する取引履歴の取り寄せ

過払い金返還請求は、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せるところから始まります。
貸金業者は、顧客から取引履歴の開示を求められたときは、開示しなければならないとされています。
監督官庁の行政処分等の抑止力が働いているため、通常であれば取引履歴は実際の取引どおりに開示されます。
取引履歴の取り寄せは、弁護士に過払い金の返還請求を依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって取り寄せすることが可能ですので、依頼者の方の煩雑さはほとんどありません。
また、取引履歴は、弁護士に依頼しなくても、ご自身で取り寄せることもできます。
一般的には、貸金業者の店舗に赴くか、貸金業者に電話することで、取引履歴を送ってもらうことができます。
2 ご自身で取引履歴の取り寄せを行う方がよいケース
取引履歴を弁護士が取り寄せれば依頼者の方の負担は減りますが、弁護士が取り寄せをしない方がよいケースもあります。
例えば、債務が残っている業者に対し、弁護士が過払い金返還請求の依頼を受けたことを理由に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をした結果残債務が残る場合は、信用情報に事故情報が登録される可能性があります。
単純な例を挙げますと、Aさんが、Ⅹ社に対し、50万円の債務を残しているとします。
Aさんが過払い金の返還請求をして、過払い金が10万円あっても、40万円の債務が残ることになります。
Aさんが弁護士に依頼して、取引履歴を取り寄せるとします。
弁護士は、Aさんから依頼を受けてはじめてAさんの取引履歴を取り寄せることができます。
Ⅹ社は、弁護士から取引履歴の取寄せの連絡を受けると、Aさんが50万円の借金を払えないため分割払いの話合いをしたくて弁護士に依頼したと理解します。
そうすると、債務整理をしたとして信用情報に事故情報を登録する(いわゆるブラックリストに載せる)よう通知することがあります。
信用情報に事故情報が登録されると、新たなローンが組めない、クレジットカードが使えない等のデメリットが発生することがあります。
このように、債務が残っている貸金業者に過払い金の返還請求をする場合は、信用情報の問題を考えなければなりません。
これをクリアするため、ご自身で取引履歴の取り寄せをし、取引履歴を弁護士にご提供いただくことで、信用情報への影響を回避しつつ、弁護士がどの程度過払い金が発生する見込みか、債務が残りそうか等を判断することもあります。
この場合は、一定期間、約束どおり貸金業者に返済を続けるのが一般的です。
このように、取引履歴を誰がどのように取り寄せるかは、弁護士と相談して決める方が安全です。
過払い金返還請求をご検討で、柏近郊にお住まいの方は、お早めに、そしてお気軽に当法人までご相談ください。
貸金業者が取引履歴を全く開示しない場合の対応
1 取引履歴の取得、検討の意義

⑴ 過払い金を請求する際の前提
過払い金が発生する仕組みを簡単に説明すると、法律上の制限を超えた利息を支払い続けた結果、本来返すべき金額を超えて利息を支払っていたことになるため、この部分を返してもらえるというものです。
したがって、まずは実際に払い過ぎた利息があるかどうかを調べる必要があります。
⑵ 取引履歴の調べ方
取引履歴の開示を受ける方法としては、業者に電話での問い合わせをしたり、店頭窓口に直接出向いて取り寄せることが可能な場合もあります。
ご依頼をいただければ、取引履歴の取り寄せから、実際に過払い金が発生しているかを確かめる作業(引き直し計算といいます)まで、全て当法人で行うことができます。
2 貸金業者の取引履歴開示義務について
⑴ 取引履歴の開示には法律上の義務がある
貸金業者には、契約についての日付、貸付けの金額、返済の金額という事項について記載された取引の履歴を作成し、保存する義務があります。
また、借主が取引履歴の開示を求めた場合、これに応じなければならないとされており、法律上の義務となっています。
これに反して貸金業者が取引履歴の開示に応じない場合には、貸金業登録の取消しや業務停止、100万円以下の罰金といったペナルティが定められています。
⑵ 貸金業者が取引履歴を開示しない場合の対応
ア 記憶に基づいて取引歴を再現し、訴訟を提起する
最初の借入の年月日、毎月の返済額、利率といった情報があれば、過払い金がいくら存在しているかを計算することは不可能ではありません。
まずは上記の方法で計算した金額を請求する訴訟を提起し、訴訟の中で取引履歴についての情報の開示を求める請求を並行して行うことも考えられます。
また、訴訟を提起すると、貸金業者側が任意に取引履歴を開示してくるということもあります。
イ 監督官庁に対して行政処分を求める申告を行う
財務局や都道府県金融課に対し、業務改善命令や、業務停止等の行政処分を求める申告を行うことも考えられます。
ただし、これらの方法で必ずしも取引履歴の開示が実現するとは限りません。
ウ 刑事告訴をする
取引履歴の開示に応じないことは法律違反であり、罰金という刑事罰が科されています。
警察署や検察庁に対し、刑事告訴をすることも選択肢の一つとして法律上は考えられます。
しかしこちらも、確実に取引履歴の開示が実現するというものではありません。
3 過払い金についてのご相談
柏やその周辺にお住まいの方で、過払い金についてのお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
過払い金返還請求を得意とする弁護士がご相談を承ります。
過払い金返還請求を得意とする弁護士の選び方
1 過払い金とは法律の制限を超えて支払ったお金

「過払い金」とは、貸金業者に返済しすぎたお金のことをいいます。
多くの貸金業者は、長年、利息制限法に規定される利率の制限を超えて、消費者にお金を貸し続けていました(いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれます)。
お金を借りるためには、借入限度額や利息等を定めた契約を締結するところ、利息制限法に規定される制限を超える部分については、契約は無効となります。
契約が無効となった部分について、貸金業者側が受け取ったお金は、法律の根拠なく受け取ったお金(不当利得)となり、これについては消費者側が返還を求めることができます。
長年、貸金業者と取引を続けた方であれば、過払い金が発生しているケースが散見されます。
2 過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求は、通常、貸金業者に対し、取引履歴(いつ、いくらでお金を借り、返したかの一覧表)を開示するよう請求することから始めます。
取引履歴に記載されている情報をもとに、適正な利率で取引が行われたらどうなるかという計算をすることで、過払い金が発生しているか否か、及び過払い金が発生している場合にはその金額を知ることができます(この計算のことを、一般的に「引き直し計算」と言います。)。
過払い金が発生していた場合、引き直し計算結果をもとに、貸金業者との交渉を開始します。
貸金業者の提示する条件に納得できれば和解に至り、和解契約に従って返還を受けて終了します。
納得できない場合、訴訟を提起して返還を請求することになります。
訴訟を提起した後においても、判決にいたる前に和解を締結することがあります。
そして、和解ができない場合、判決を得ることになります。
3 過払い金返還請求に関する弁護士の選び方
⑴ 弁護士が取り扱う分野
弁護士が扱うことができる分野は、極めて幅広く存在します。
全ての分野を一人の弁護士が万遍なく扱うことは不可能ではありませんが、それぞれの分野にかけることができる時間や労力は分散されてしまうため、理解や経験は浅いものとならざるを得ません。
逆に、弁護士が一定の分野を中心的に取り扱い、ノウハウや経験を蓄積している場合には、当該分野を得意分野としていることになります。
⑵ 過払い金返還請求を得意とする弁護士
柏市周辺に限られたことではありませんが、一般的に、すべての弁護士が過払い金返還請求を得意としているわけではありません。
過払い金返還請求には、多くの論点があるため、弁護士がこれらの論点に関する知識や経験が十分でないと、思っていたよりも少額の過払い金しか返還されなかったり、消滅時効が完成してしまったりという事態も考えられます。
過払い金の論点に対する裁判所の判断も、日々動いています。
少し前までは、結論がほぼ固まっていたとされていた論点についても、再度判断が割れだすこともあり、貸金業者側はそのことを強く主張しだすこともよくあります。
また、貸金業者ごとに過払い金返還請求に対する対応が異なるので、貸金業者ごとの特色を抑えておく必要もあります。
⑶ 過払い金返還請求を得意とする弁護士の選び方
このように過払い金返還請求を得意とする弁護士を選ぶには、過払い金返還請求の経験が豊富で、貸金業者との交渉に慣れているか、という観点で検討することが大切です。
法律事務所のホームページにおいて、過払い金返還請求や債務整理の実績が掲載されていれば、その事務所が過払い金返還請求を得意とするか判断するための材料とすることができるでしょう。
4 柏にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
弁護士法人心では、分野ごとの担当制をとっており、債務整理に精通している弁護士が複数在籍しております。
柏近郊にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方は、お早めに、弁護士法人心にお気軽にご連絡ください。